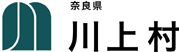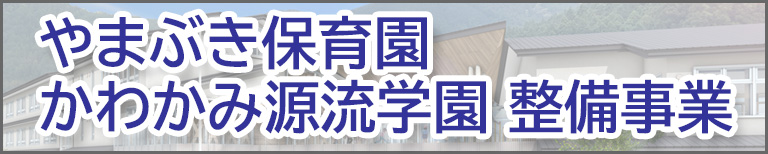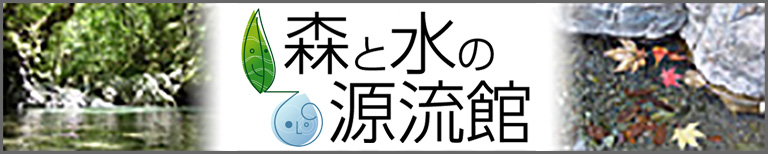公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 金剛寺
- 所在
- 神之谷金剛寺
- 時代
- 江戸時代
このお寺は、修験道から始まったお寺との言い伝えがあり、山号を「妹背山」と呼ぶのは、その辺の事情を語っているような気がします。寺の名前は、後醍醐天皇の命名であるという言い伝えもある古刹(こさつ=古いお寺のこと)です。
当初の建築材が妻飾りなどで残っていますが、虹梁(こうりょう=外に掛け出した屋根部分を支える柱と内陣の外柱をつなぐ用材のこと)の部分に上棟の時の墨で書かれた記録(墨書)が見つかりました。それによると、江戸時代の享保3(1718)年、大工棟梁(とうりょう=親方の名前)田中覚右衛門以下11名により建てられたとわかりました。調査に当たった松本技師は、「近隣に類の少ない本格的な寺院建造物だ。」と語られております。奈良県教育委員会発行「奈良県の近世社寺建築」にも掲載された貴重な江戸時代の建造物。昭和54年村文化財に指定。(寺の建築年代は諸説あり)
この寺は、別名「那迦寺(なかでら)」「大峰山上奥之院」とも呼び、東部の皆さんは「なか寺」と親しんで来たお寺です。寺伝では、奈良時代「役の行者」の創建となっています。堂の階段を登った所を「向拝(ごはい)」と呼び、仏殿に向かいお拝をする場所です。なお、仏像等の拝観は平常無理ですが、本堂はいつでも拝観できます。