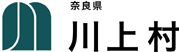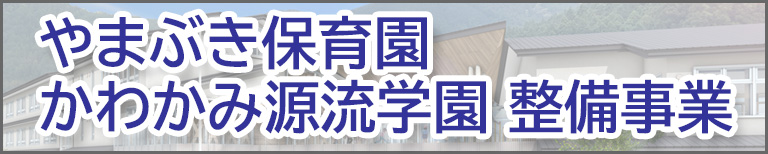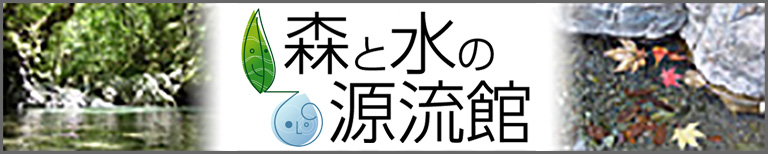公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 福源寺
- 所在
- 高原902番地
- 時代
- 南北朝時代
「あいかわつつみおおそで」と呼びます。「藍」とは染め物に使う言葉です。「韋(かわ)=皮・革」のことで、古来の表現です。
これは、戦いに使われた武具の一つで、体を保護します。肩から両腕にかけての部分を弓矢から守る武具で、村では、国重要文化財である後南朝の遺品の中にも「大柚」があります。いずれも南北朝時代の優秀なものです。その他「兜(かぶと)・胴丸(どうまる)も同じ武具の一つです。
この寺の大柚は、時代としては国の重要文化財と同時代のものと言われていますが、国の重要文化財の大柚が自天王の遺品として保存されてきたのに対し、弟忠義王の遺品として伝えられて高原で保存されてきました。
普通「兜・胴丸・大柚」は、使われている材料により名前が決められています。この大柚は、国重要文化財の大柚よりやや劣るものの、藍色で染めた皮で包んだ大変良い出来ばえのものとの判定で、村文化財に指定されました。
また当時(南北朝時代は室町時代の一時代で、今からおよそ約600年ほど前)、兜や胴丸を造る技術が新しい方法に変化してくる節目に当たると言われていますが、この大柚は、古式の大柚であるということですから、大変貴重な文化財と考えられます。