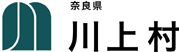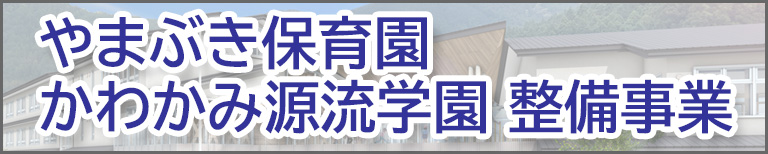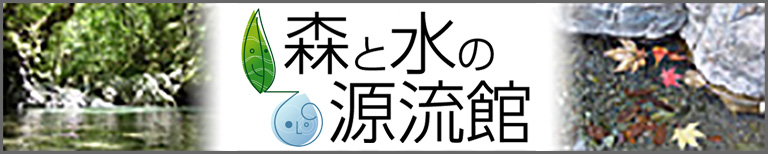公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 奈良県
- 所在
- 入之波ごうすぎ谷
- 燵石周辺
燵石(ひうちいし)というのは大変めずらしい地名です。その昔、火を起こす道具として「火打石」が使われました。白色で青味を帯びた石英岩と火打金をすり合わせ、飛んだ火花を火のつきやすい布などに移して布を燃えさせ、柴などに火を移しました。「燵石=火打石」のことです。火打石の材料となる石が採掘されたので、こうした地名になったのでしょうか。
この辺一帯の谷川の流れの中にある岩などに、自然に生える藻(も)の一種の集まりが「かわのり」です。山間の谷川などに生える緑色した藻でもあり、カワノリ科に属します。日本の特産種で、体は薄い緑色の葉状膜質でできており、長円形や楕円形に伸び、長さ数cm~約20cmの緑辺が波状になった藻です。大変めずらしく、生える場所も毎年同じ場所とは限りません。自生する場所の条件が、出水や洪水その他の自然条件によって大きく左右されます。最近は、燵石より他の近くの谷川に自生しているのが発見されることも多くあります。
「海ノリ」に似て食用が可能です。昔の人々は、これを採取して食べていましたが、文化財となった今では食用への利用はできません。きれいな自然から、こうした自然の贈り物が得られるのも山の幸と呼ばれるゆえんでしょうか。