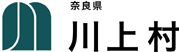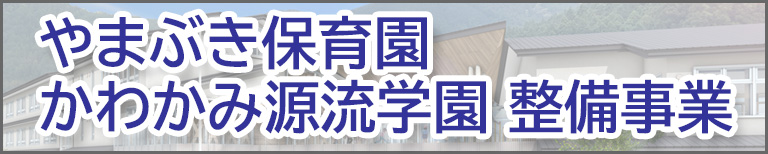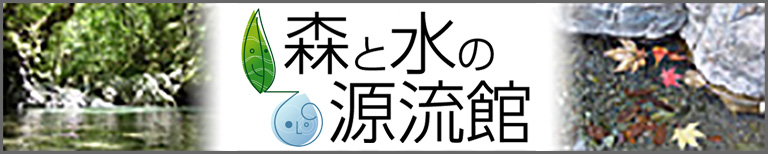公開日 2023年6月15日
2千有余年の歴史ある村
川上村の歴史は、出土した遺物によると縄文時代までさかのぼることができます。古事記、日本書紀には神武天皇の井光や雄略天皇の蜻蛉野(あきつの)にかかわる地名伝承もあります。万葉の時代には天皇行幸や歌人が訪れるなど、古くから景勝の地として知られていました。
木地師(きじし)の祖である惟高(これたか)親王は、貞観九(867)年に高原地区に入り、木地の製法を教えたといわれています。福源寺には、応徳二(1085)年の木造薬師如来坐像があり、井戸地区には承安三(1173)年に造られた木造の薬師如来像もあることから、すでに平安時代後期には、高原や井戸地区には集落が形成されていたと思われます。
また、川上村には、源義経伝説を物語る太刀屋や鎧崖といった地名もあり、中でも白屋地区には、今まで白谷と称していた地名を義経が八幡神社に矢を奉納したことから白矢と改めたという言い伝えが残されています。さらに、天武天皇四(675)年に創祀されたと伝えられる丹生川上神社上社や十二社神社、牛頭天王神社、三之公神社、天神社など謂れある神社がいくつも散在しています。また、東川の運川寺には、正平十四(1359)年に書き写された大般若経六百巻も所蔵されており、川上村の深い歴史の片鱗を知ることができます。
早くから温泉地として開けた入之波(しおのは)温泉は、元禄七(1694)年に、「御夢想塩湯」という版木を使って宣伝していました。村人の娯楽としては、人形浄瑠璃や歌舞伎などの地芝居が盛んになり、井光地区には、当時地芝居に使った衣装が数多く残っています。
哀しくもロマンあふれる南北朝時代
川上村は後南朝の舞台としても歴史に名を連ねています。
1336年に後醍醐天皇が吉野に御座を移されてから約60年。元中九(1392)年、足利義満の呼びかけに応えて後亀山天皇が京都に遷幸され、南北朝の歴史もようやく幕を下ろしたと思われました。しかし「皇位は両朝交互に与えられる」という約束も守られず、南北朝の合体は実質的には南朝の消滅となりました。後亀山天皇の皇子、実仁親王は、幕府に抗議し戦いますが、川上村に潜幸され、嘉吉三(1443)年に崩御されます。そして、同年ついに「嘉吉の変」に乗じ、小倉官の皇子である天基親王と円満院宮が京都へ進攻して三種の神器のひとつ神璽(しんじ)を奪い、吉野南山に御所を置きました。
一方この変が起こる以前に、天碁親王と円満院宮の弟・尊義王は近江から川上郷に移り住んでおり、尊義王は兄の円満院宮から神璽を譲られ、皇子の尊秀王(一ノ宮、自天王)と忠義王(二ノ宮、河野宮)を連れて、三之公(さんのこ)に御所を構えました。しかし、尊義王は南朝の再興を果たすことなく45歳で病死してしまいます。
その後、自天王は北山郷(奈良県上北山村)に、忠義王は河野谷村(神之谷)にそれぞれ御所を構え、南朝の夢を果たそうとします。ところが、嘉吉の乱により滅ぼされた赤松家の家臣が、お家を再興させるため、当時、北朝方や将軍家が血まなこになって探していた神璽を南朝から奪回することを企てました。
長禄元(1457)年12月2日の夜、赤松の家臣により2つの御所が襲撃され、自天王は18歳の若さでこの世を去り、忠義王は御所で討死、あるいはその場は死地を脱したものの、本村の高原で最期を遂げたと伝えられています。
この惨事はいちはやく川上郷に伝えられ、郷土たちは、自天王の首と神璽を手に逃走する赤松の郎等を迎え撃ちます。塩谷村(北塩谷)の名うての射手・大西助五郎は、郎等の頭であった中村貞友を見事射止めたと伝承されています。郷士たちは皇子の首と神璽を取り返し、首は金剛寺に手厚く葬られたと伝えられています。しかし1458年、赤松の残党に神璽を奪われ、これによって赤松家はお家再興の悲願を達成します。
このように後醍醐天皇から始まった南朝の血は絶え、南北朝の動乱は終焉を迎えましたが、川上郷土たちの雄志は代々語り継がれ、毎年2月5日には、自天王を偲び、新年拝賀の儀式として朝拝式が、560年あまり経っても絶えることなく今日まで続いています。