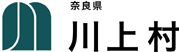公開日 2017年9月12日
去る2017年8月10日~8月23日の計14日間、川上村において地域づくりインターンシップとして学生2名を受け入れ致しました。
川上村は奈良県の南東部に位置し、500年の歴史を持つ吉野林業の地で、大滝・大迫ダムと緑のダムを抱える水がめの村です。吉野川・紀の川の源流から清らかな水を流域に届け続ける村づくりをしています。地域づくり、林業や環境教育などに興味がある学生を対象に、滞在型のインターンシップを平成10年度から実施、参加学生は延べ50名を超えています。
『地域のために、村民の暮らしのために、ともに動き、考え、動く。』
参加した2名の学生がこのインターンシップを受け、自身のネクストアクションとして何ができるかまとめました。それぞれの視点からの未来への動きとして皆様もご一読いただければ幸いです。
川上村で過ごして考えたネクストアクション
奈良女子大学 生活環境学部 3年 桑原湧
1.参加したきっかけ
去年の川上村地域づくりインターンシップに参加した、同じ大学に通う友達に話を聞いて楽しそうだなと思ったのがきっかけです。村での暮らしや自然、村役場での仕事内容にも興味がありました。
2.活動を通じて学んだこと、感じたこと
●かわかみらいふ
事務局長の竹内さんから営業の秘訣「お客さんがどうすれば喜ぶかを考えて行動。」と教えてもらいました。また、「ぼちぼちでいいよ~」という言葉も印象に残っています。(期間中、別の機会にもこの言葉を聞く機会がありました。)そして村の人の役に立ち、喜んでもらえるとうれしかったです。

●盆踊り大会
東部地区盆踊り大会と東川盆踊り大会に参加しました。
午前中の準備では、やぐらを組んだり、提灯を付けたり、みんなであれやこれや言いながら準備するのが楽しかったです。村の方に気さくに話しかけていただき嬉しかったです。
どちらの盆踊りでも、生歌と生太鼓に合わせて踊るという本格的な盆踊りでした。

東部地区の盆踊り大会。大きな山と川に囲まれて。(準備風景)

東川盆踊大会。歴史ある烏川神社で。
東部地区盆踊り大会では、1時間半の間、盆踊りを踊り続けました。村民の方の言葉を借りると“無我の境地”へ陥りました。また、スタッフとして、みたらし団子を淡々と焼き続けました。いい焼き色になってきたと思ったら、ひっくり返す。盆踊りも、みたらし団子焼きも、気持ちがすっきりとするような素敵な体験でした。
東川の盆踊り大会では、焼き鳥を担当しました。盆踊りを踊ったり太鼓やサックスの演奏も聴きました。太鼓の演奏は、まさに魂の打ち込みで、圧倒されました。サックスはとても優しい音色での演奏でこちらも引き込まれました。いつか、太鼓もサックスも挑戦してみたいと思っています。
どちらの盆踊り大会でも、村の方が子供たちにたくさん話しかけている姿が印象的でいいなと思いました。
●森の中にたたずむ温泉
入之波温泉山鳩湯。森の中にあって冒険心をくすぐられました。露天風呂から、森林と川の景色が望めます。ぬるめのお湯につかりながら、緑を見るのはとても癒されました。
●不動窟
身をかがめないと通れないほど狭い場所もあったりして、自然のまま残されている感じが素敵でした。洞窟の中の滝というのも神秘的でした。
●吉野川本流の支川はとても綺麗な川でした。水が本当に透き通っていて、今まで見ていた水は本当の透明ではなかったのだなと思いました。
●水源地課の今福課長に、星空が綺麗に見えるところにも連れて行っていただきました。普段見ている星の何倍もの量の星が見えました。天の川も綺麗に見えました。ベンチに寝そべると、視界いっぱいに星空が広がって、昔の人たちもこんな風に星を眺めていたのかなと思いました。大きい流れ星も見ることができました。(この場所で後日、星空観察会がありました。)

●河川パトロール
役場水源地課の業務のひとつ、河川パトロールに同行し、車内からごみの持ち帰りのお願いのアナウンスしました。

「お願いするような気持ちで優しく言ってね。」という言葉や、川に遊びに来た子供たちに「楽しかった?」と尋ねている姿に、役場の職員さんの人柄の暖かさを感じました。
お昼休み、清流を眺めながら、岩の上で食べるお弁当とカップラーメンは格別でした。また、大きい岩の上を4足歩行で渡り歩く楽しさを発見しました。子どものころにあこがれたもののけ姫に少し近づけた気分でした。
役場の方が「子供のころ川に潜ると、視界がきらめいて、“きらきら”と音がするようだった。」とおっしゃっていました。今度来たときは、川に潜りたいと思います。
●水源地の森トレッキング
水源地の森トレッキングでは、言葉では言い表せない生きるパワーをいただきました。岩に寝そべらせてもらったりもしました。目に映る黄緑色は初めて見る黄緑色で、とても美しい色でした。

実は、川上村に来るまでは、川の水がどこから来ているのかなんて考えたこともなかった私でした。雨が降り、山に水滴が染み込んで、それが小さな流れを作り、小さな流れがどこかで合流してやがて滝や川ができるんですね。
水源地の森では、大きな川の源流となるであろう小さな川やたくさんの湧水(小さな滝みたいなもの)を見ました。こんこんと湧きだす水の流れを見て、言葉でいうのは難しいですが、何かが生まれてくるってすごいことなんだなあと思いました。

上の写真は、大きい川の源流である小さな川です。小さな川の水も飲みました。生まれたての川の水です。水を飲むのなんて当たり前にしていることなのに、ここで水が生み出されたからこそ、普段水が飲めているのだと思うと不思議な感覚でした。
あふれだす水に生命力を感じます。
水源地の森トレッキングでは、様々な草木の紹介もしていただきました。とても興味深かったです。山と密接に関わって生きてきた方の知恵を伝承したいと思いました。
●林業レクチャー
急な山道を登って、今回林業レクチャーを行う場所へ向かいました。それだけで私は息が切れて、足がしんどくなってきたので、毎日山に入って仕事をしている方への尊敬の念が湧きました。
山に着くと、初めにカントリーマアムをお供えして、山への感謝の気持ちを述べました。山の木々は私たち人間よりも大分年上であったりもするので、敬意を表す必要があるとのことでした。この儀式を体験して、私は、人間が自然を支配してきたのではなく、自然の力を借りる気持ちで、自然と共生してきた歴史を感じました。そう思うと、木を使った製品により愛着を感じました。
そして、実際にのこぎりで木を伐らせてもらいました。細い木だと思っていたのに実際に切り始めると腕が辛くなってきて、途中で切るのを投げ出そうかと思うほどでした。こうやって一本一本木を切るという地道な作業を、山のお手入れのために200年以上前から続けてきた人々がいたと知り、とても尊敬する気持ちになったと同時に、そのおかげで今の吉野の木があるのだと分かりました。
自分で、木を伐らせて頂けたのは、これからの木に関する学びのベースとなる貴重な経験でした。
次に、高原の森に移動しました。舗装されていない山の急斜面を登るのはしんどかったけれどとても楽しい経験でした。全身の力を使ってバランスをとりながら進むので全身がポカポカしました。現場には大きくて太い木がたくさん根をはっていました。木が倒れる瞬間も少し離れた場所から見ていました。倒れた時に地響きがしてとても迫力がありました。自分が小人になった気分でした。

一番、心に残ったのは、木の皮をむかせてもらったことです。一枚、木の皮をはぐだけで、しっとりと水分を含んだきめの細かい面が現れます。木って美しいなと思いました。
皮を剥ぐときに使った木製のヘラは、山守さんたちがずっと使ってきたものだからか、貫録あるきれいな飴色をしていて、手に持っているだけでずっしりと安心感があるような一品でした。木の小物っていいなと感じた瞬間でした。

この森の神様にもお酒をお供えしてありました。
先ほどと同様、人間が自然を支配しようとしてきたのではなく、自然と共生してきた歴史を感じました。木製品への愛着がさらに湧きそうです。
下山後にバーベキューも開催してくださいました。林業レクチャーで間伐した木で、講師の玉井久勝さんがその場でつくって下さった木蝋(もくろう)がいい味を出していました。この上に鍋などを置いて温めました。

●山の中にあった木は、実際どんなふうに使われるのだろう。加工の現場見学。
林業レクチャー2日目にお世話になった泉谷木材商店では、吉野杉や吉野檜の木材がたくさん取り扱われていました。
泉谷繁樹さんの解説を聞いているうちに、きれいな木目や色をしている木が分かるようになってきました。
木目が細く同じ幅で入っている木材がきれいだとか、白いけれどほんのり赤みがかった色がきれいだとか(例えると赤ちゃんのほっぺのような)いうことが分かってきました。
200年の間、人々が1本1本、木を切って山をお手入れし続けてきました。(前日の林業プログラムで急斜面の中を歩くのがどれだけ大変か、1本の木を切るだけでどれほど腕力を使うかは実感しました。)そのおかげで、こんなにきれいな木目ができたかと思うと、とても気の長い芸術品だなと思いました。

振り返ってみると期間中に滞在していたシェアハウスは心が落ち着きました。歩くたびにこの家を大事にしようと思えました。時間がたつと綺麗なあめ色になっていくらしいです。

●木を使った小物
写真は、吉野かわかみ社中の盃と泉谷木材商店のつみきです。
川上村では、たくさん木を使った小物に出会いました。きっと長く使えば使うほど手になじんでいくのだろうなと思います。林業レクチャーの時に、長く使われてきた木製のヘラを手にして確信しました。
大切な人への贈り物にぴったりだなと思います。


●やまいき市
やまいき市で働いた感想としてまず出てくるのが、楽しかったということです。そしてとてものどかでした。
岩本さんは「ぼちぼちでいいよ~」と声をかけてくださいました。
エリックさんは、店番をしながらたくさん面白い話をしてくださいました。
朝、野菜の集荷をしに高原の集落まで行きました。90歳の女性がとても元気に話しかけてくれました。帰りに、野菜が全部売れたことを伝えるととても嬉しそうでした。
野菜を作ってやまいき市で売るということが、生きがいの一つになっていることが伝わりました。

●星空観察会
星空の下でピアノの演奏を聴けるという贅沢を味あわせていただきました。山川亜紀さんが演奏したフレンドという曲が私は特に好きで、素敵なひとときでした。写真家の辻本勝彦さんが紹介する川上村の美しい風景が次々に映し出され、大滝ダムなど行ったことのある場所もありましたが、時間帯によって姿を変えるようで、夕日をバックにした大滝ダムにも行ってみたいなと思いました。
●自由行動で、蜻蛉の滝にも行きました。周回ルートがあり、わくわくした気持ちで滝を探すことができました。
3.私が伝えたい川上村の魅力
・原生林・川の水・湧水・滝・星空が綺麗。
・いつでも大きな森の景色が目に入るのが安らぐ。
・料理や飲み物がおいしかったです(できたての水で綺麗だからだと思いました)。
・子どもが伸び伸びとしていると思いました(村の図書館で出会った子供たちも。)。
・年配の方も役割を持ち、元気だというのは希望が持てる社会だと思いました。
・期間中、楽しく働けました。
・人が優しい、皆さんいい意味でアバウトな方が多いと感じました。素敵な方にたくさん出会えました。
4.ネクストアクション
●川上村とのつながりから
・山と共生するための知恵を聞く、今伝承しないといけないと感じました。
・どんな活動でも、一人ひとりに役割があってお互いに感謝し合あいたいと思います。
・自分のためにも高齢者の方にもっと積極的に関わっていきたいです。
・利益をあげることは大切だけれど、ベースに人を思いやる気持ちを忘れないでいきたいと思いました。
・都市部でも移動スーパーのような気軽に集まれる場所を考えたいと思いました。
●川上村とのつながり(特に、林業・木のことに関して)から
・自分の家を建てるときに吉野杉や吉野檜が頭をよぎると思います。
・木を使った小物に興味を持つようになり、使えば使うほど木のぬくもりを感じられそうです。大切な人への贈り物にいいなと思うようになりました。
・自分で、木を使った商品で何が欲しいか考えるようになりました。
・子どもたちにたくさんの木の家で過ごす等の木とのかかわりを持ってほしいと思うようになりました。
●個人的な指針
・自分の部屋を掃除します。物が多いから…ここに滞在したら、暮らしを見つめることができました。
・2週間の日々について絵日記にしたいと思っています。
・知らずしらずのうちにきっちりするのが良いと思い込んでいたのですが、良い意味で適当にするのも大事。感動はゆったりした心から生まれると感じました。
・たくさんの経験をして、これからも豊かさについて考えていきたいと思います。
●川上村でたくさんの魅力を発見したので、その魅力を周りの方々に伝えていきたいと思います。