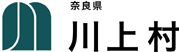公開日 2017年11月24日

ライター:渡辺直樹(「むらメディアをつくる旅」事務局)
編集協力:早稲田緑(川上村在住、元川上村地域おこし協力隊)
2017年10月28日(土)〜29日(日)に、「奈良の木マルシェ〜山からのおくりもの〜」が開催されました。(主催:奈良の木づかい運動実行委員会)
川上村も開催協力しているということで、28日(土)に参加。道の駅吉野路大淀iセンターの木に囲まれた空間で、おいしいもの、木工品、人のつながりといった“山からのおくりもの”に恵まれた素敵なマルシェでした。
●山と500年以上つきあってきた吉野からのメッセージ


「山からのおくりもの」というキャッチコピーのとおり、マルシェでは吉野の山からきた食べものや木工品がずらり。道の駅には色んな目的をもつ人たちが立ち寄りますが、マルシェのために来た人もそうでない人も、何やら木のやさしい香りに誘われてふらりと訪れます。マルシェの入り口には、どどんと吉野杉の酒枡を積み上げたオブジェが出迎えていました。木の香りを楽しむ人、かわいらしい木工品を見て楽しむ人。木工品には、川上村のアーティスト「白い犬」さんも出品されていました。

(「白い犬」さんの作品たち)

(吉野の柿の葉寿司たち)

(吉野の日本酒たちも)
●山の人たちとつながるマルシェ

奈良の木マルシェは、作品や食べものだけでなく、山の人たちともつながることができるのが特徴です。マルシェの中央部では、トークセッションとして出展地域の人たちが「山からのおくりもの」について紹介してくれました。例えば美吉野醸造の橋本さんは、木桶と日本酒を通じて山と川と人が結びついていること、樹齢100年の木が木桶に向いており、おいしくて味わい深い日本酒を楽しむには100年続く林業が必要なことを語ってくださいました。こうしたつながりを感じながら飲む日本酒は、いっそう深く味わうことができそうですよね。

他にも山仕事の様子や、吉野の山から切り出された木が貯木場で売られ製材されていく様子、それが子ども向けの木のオモチャや小学校の机に活用されている事例なども紹介されました。
私自身は、川上村を訪れる中で早稲田緑さんに出会い、早稲田さんが運営メンバーということでマルシェのことを知り、山のことをもっと知りたいなという気持ちで足を運びました。そんな人もいれば、道の駅ということでたまたま訪れて、柿の葉寿司や木工作品を見て「おおっ」と思っていたら、何やらトークが始まったので聞いてみた…という人もいたでしょう。こうして色んな人たちが1つの空間と物語でつながる、そんなところが大きな魅力だったように思います。
皆さんも、思い当たるモノの起源をぜひたどってみてください。山からのおくりものが目の前にたくさんありますよ。