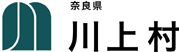公開日 2024年5月27日
令和5年度決算における健全化判断比率等
自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すため財政健全化法が制定され、健全化判断比率として四つの指標及び公営企業の経営状況を示す指標が定められました。健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
法律の規定に基づき、令和5年度の実績値を公表します。
令和4年度決算に基づき算定された川上村の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、すべて基準を下回りました。
ただし、川上村の財政が厳しい状況であることには変わりなく、これからも行財政改革を徹底して行います。
健全化判断比率
| 指標名 | R4年度実績 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | - (△18.59%) |
15% | 20% |
| 連結実質赤字比率 | - (△20.35%) |
20% | 30% |
| 実質公債費比率 | 8.6% | 25% | 35% |
| 将来負担比率 | - (△169.8%) |
350% | - |
※実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担額がないため「-(該当なし)」で表示し、参考値として黒字の比率を(△)で示す。
資金不足比率
| 会計名 | R4年度実績 | 早期健全化基準 |
|---|---|---|
| 簡易水道特別会計 | - (△20.35%) |
20% |
※資金不足比率がないため「-(該当なし)」で表示し、参考値として資金剰余 の比率を(△)で示す。
財政の健全度を判断する指標
4つの指標で判断します。
- 実質赤字比率
地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。 - 連結実質赤字比率
全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。 - 実質公債費比率
借金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。 - 将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
公営企業は次の指標で判断します。
- 資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。
財政指標の対象会計範囲のイメージ

判断の基準
各指標の基準は次のようになります。
いずれかの早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」となります。それより悪い財政再生基準を超えると、従来の財政再建団体にあたる「財政再生団体」となります。

※1:市町村の早期健全化基準は、財政規模に応じて異なります。
※2:連結実質赤字比率の財政再生基準は、導入期の3年間のみ5~10%引き上げられます。
※3:将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
また、公営企業会計についてはこのようになります。 経営健全化基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定が必要となります。

早期健全化(イエローカード)になると
財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。
財政の再生(レッドカード)になると
財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むこととなります。総務大臣の許可が得られなければ地方債の起債が出来なくなります。また、税金や公共料金の増額、住民サービスの見直しをせざるを得なくなります。
計画の実施状況
計画の実施状況は毎年9月30日までに公表されます。取り組みが不十分な場合は、健全化段階では国または県が、地方公共団体に対し必要な勧告を行うこととなります。財政再生段階においては国が、地方公共団体に対し予算や計画の変更などの措置を講ずるよう勧告し、より強く財政運営に関与することになります。
議会や監査委員との関係
財政健全化法では、議会や監査委員の役割が重要になります。
- 各指標の数値は、監査委員の審査を受けた上で議会に報告し、公表しなければなりません。
- 早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する際には、議会が議決し、住民に公表されます。
また、その実施状況を毎年議会に報告し、公表しなければなりません。 - 早期健全化団体・財政再生団体は、計画を策定するにあたり、財政健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について外部監査を受けなければなりません。