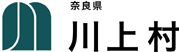公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 十二杜神社
- 所在
- 井戸845番地
- 時代
- 江戸時代
下井戸のバス停から在所を通 り、林道を登ると寺の下に出ます。さらに橋を通過し、林道を行けば「十二鳥居をくぐりぬ け、境内本殿への参拝殿の右横手に安置されている灯籠が「おかげ灯籠」です。高さ約2mありますが、この灯籠の特徴は、右側に幟(のぼり)を立てている着流し男の姿が彫られていることです。
その昔伊勢参りコースは、村内を通っていた東熊野街道を南東に進んで熊野から伊勢に向けて北上、伊勢街道を経過して伊勢神宮に参拝したものであろうと想像できます。 ●今でも「伊勢講」が残っていますが、お伊勢さんの「お蔭」をこうむりたいという願いで、踊りを踊って記念に灯籠を建てたようです。明治に近い頃になりますと、全国的に政治・経済が破綻状況となり、「おかげ踊り」はやがて、「ええじゃないか踊り」に発展し、明治維新への大きな変革のうねりの中で、世の中が大きく変化することになります。
この神社は、回りの木々を伐採して明るくなりました。県内に数多く残る「おかげ」関係の歴史遺産の一つで、絵が描かれた灯籠はここ井戸の灯籠だけであり、県内での貴重な民族習慣を伝える石造文化財となっています。