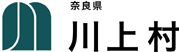公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 観音寺
- 所在
- 井光348番地
- 時代
- 江戸時代
このお寺は井光の入り口にあり、その名の通 り「十一面観音菩薩」が本尊様です。開創は江戸時代延宝年間(元年=1673年)とされていますが、本尊は平安時代の仏像であることがわかりました。他から招かれた仏様かも知れません。
この寺には、村指定文化財の梵鐘(ぼんしょう一つり鐘のこと)があり、江戸時代宝暦元年(1751)に鋳造(ちゅうぞう)されました。鐘中央部(撞木座上部)に釈迦像と阿弥陀像の2体の仏像が、浮かし彫りのように鋳込(いこ)まれており、見方を変えれば、鐘そのものが信仰の 対象とされてきたとも言えます。
太平洋戦争の時、国は金属不足のため全国各地寺院の梵鐘など金属の供出を要請しました。しかし、当寺の梵鐘は、歴史的に由緒あるものだという地元の陳情が出され、知事によりそれが認められて供出を免れています。「仏像が彫られた梵鐘を戦争の道具に使うとは何事ぞ?」ということだったのでしょうか?当時全国では、大変貴重と言われた多くの梵鐘も供出を余儀なくされた経緯があり、当時の井光や川上村で、県知事をも動かすことができるはどの力が存在したか、よほど強運だったか縁が強かったか。こうした見方も、文化財を鑑賞する楽しみの一つです。本当のところは知るよしもありませんが…。
井光は、「いびかの里」として養魚場や井光の休憩所(在所の人の運営)などが整備されており、新国道から一部新道も完成していますので、一度散策されてはいかがでしょうか?