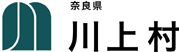公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 福源寺
- 所在
- 高原902番地
- 時代
- 平安時代
このお寺は、惟喬親王(これたかしんのう/木地師の祖と呼ばれ文徳天皇の子ども)の木地師にまつわる言い伝えのある寺です。また後南朝の位 牌もまつり、修験道にかかわる歴史もある寺です。
本堂にまつられるこの仏像は、像の高さ48.1cmで桧材から造られています。西河の徳蔵寺釈迦如来と同様、平安時代の定朝様式の流れをくんだ彫刻で、専門家は珍しい作例であると語られています。この仏像は、昭和63年村史編集の調査中で発見されたもので、調査に当たられた紺野敏文さんは、「肉髻珠(にっけいじゅ/お釈迦像が生きておられた頃に、頭の前部に肉の盛り上がった部分があったとの言い伝えがある。)や白毫(びゃくごう/釈迦像の額の中央部にある珠のこと)は後日修理の時に新しく交換された。」とも語っておられます。その他の部材では、当初のものが残っているようですが、本尊様としておまつりされてきたこともあって保存状態もよく、しっかりした形を留めている大変形の整ったお姿です。
普段はなかなか目にふれることのない仏様ですが、ホテル杉の湯付近から高原の里を訪ね、このお寺にお参りするのもまたこれ楽しい道のりではないかと思います。最近道路が整備され、車でも行けるようになりました。特にこのお寺では、後日紹介する重要文化財の薬師如来やその他数々の文化財を保有する寺でもあります。