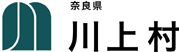公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 徳蔵寺
- 所在
- 西河649番地
- 時代
- 室町時代
この仏像は、徳蔵寺の本堂正面 の、向かって左側に位置する場所にまつられている、像の高さ39.2cmのやや小振りの桧の仏像です。当初は「薬師如来」ではないかと言われましたが、その後の調査で、薬師如来の特徴である手の平の薬壷の跡がないことから、阿弥陀如来と判定されました。
当寺の「釈迦如来」と同じく写真集の掲載やテレビ放映されたこの仏像は、14~5世紀頃奈良で活躍した仏師集団「宿院仏師(しゅくいんぶっし)」の一人が彫刻した仏像で、その彫刻の仕方から「壇像(だんぞう)」と呼んでいます。
体内の墨書銘によれば、『大仏師源三郎。酉年。天正元年拾月吉日。奈良林小路。空阿堂子源三郎』となっています。天正元(1573)年は、室町時代の終わり豊臣秀吉や安土桃山時代初めの頃です。
平成10年奈良県教育委員会発行の「宿院仏師(戦国時代の奈良仏師)」にも紹介されていますが、それによれば、「源三郎」は宿院仏の終わりの頃、今の奈良市で活躍した仏師だったようです。