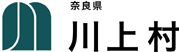公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 徳蔵寺
- 所在
- 西河649番地
- 時代
- 平安時代
このお寺は、近畿内三庚申の一つがまつられており、お堂には、「猿の縫いぐるみ」(身代わり猿とも、庚申のお遣いとも言われる)が多数納められています。江戸から昭和にかけ、祭礼には多数の露店が立ち並び、村内外の方々も多数参ったと言い伝えられています。
「釈迦如来坐象」は、庚申堂の近くの釈迦堂の本尊で、どこから移されたか不明ですが、寺では、「客仏」(他から入ってきた仏像)と呼んでいます。像の高さが94cmの桧の木像で、平安時代の定期様式(定朝という仏師が造った仏像)の影響が見られます。写 真集「大和路かくれ寺かくれ仏」(昭和57年発刊)に掲載され、奈良テレビ「奥吉野の仏像」でも、慶応大学の紺野敏文教授の説明で放映されました。地元では「黒ん坊」の愛称で親しまれ、子供のいたずらが過ぎると「黒ん坊さんとこ行こか?」と言えばおとなしくなったと言われるほど真っ黒(漆の下地の色)ですが、立派な堂々としたお姿です。仏像と保存の堂も、文化財補助を受けて改修されました。
なおこの寺では、3月の最終日曜に庚申さんが催され、庚申像と庚申掛軸展が開かれます。「庚申さん」の本尊(約10cm弱)は、60年目の庚申(かのえさる)の年に開帳する秘仏として伝承されています。こうした機会に、文化財を拝観するのもよいかと思います。奈良交通 、西河バス停から遠望できる山腹のお寺です。