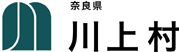公開日 2022年5月30日
国民年金とは
老後の生活を充実した実り豊かなものにするためには、経済的な安定が欠かせません。老後の生活を保障し、私たちの暮らしを支えてくれるものの一つが、公的年金制度である国民年金です。また、国民年金制度では、思わぬけがや病気で障害者になったときや、一家の働き手を失ったときにも、年金が給付されます。
国民年金加入者
国民年金には3つの種類があり、日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ずどれかに加入します。
学生の方も20歳になったら加入の手続きをして保険料を納めなければなりません。
加入者の種類
| 第1号被保検者 | 学生・農林業などの方とその配偶者・自営業者などの方 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 被保険者年金制度の被保険者(会社員または公務員)などの方 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
また、次の方は希望すれば加入することができます。
・国外に住む日本人(20歳以上60歳未満)
・国内に住所のある60歳未満の方で、老齢(退)年金を受けている方
・国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(特例で70歳までの任意加入制度あり)
詳しくは「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
保険料額について
保険料は、20歳から60歳までの40年間収めることになっています。
保険料の納め忘れがあると、将来、受けられなくなったり、減額されることがありますのでご注意ください。
令和4年度 保険料額
|
定額保険料
|
1ヶ月
|
16,590円
|
|---|---|---|
|
付加保険料
|
1ヶ月
|
400円(月額)
|
前納制度
1年分または半年分をまとめて前納すれば、保険料が割引になる制度です。口座振替でも前納できます。
免除制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難な方は、申請して承認を受けると、保険料の納付が免除されます。10年以内であれば後から納めることができます。
また、学生の方には学生納付特例制度があります。学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請して承認を受けると、その期間の保険料は猶予されます。
納付について
納付書は日本年金機構から送付されます。銀行、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法と、口座振替の方法があります。
こんな時には届出を
就職や退職、結婚などさまざまな人生の節目には、役場の国民年金係の窓口で届出をしてください。届出をしておかないと、将来年金が受けられなくなったり、減額されることがありますのでご注意ください。
第1号被保険者
|
どんな時
|
届出方法
|
用意するもの
|
|---|---|---|
| 会社等に勤めていない人や学生が20歳になった時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 印鑑 |
| 配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶者となった時 | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 年金手帳・印鑑 |
| 海外へ転出する人が、引き続き時 | 役場国民年金係または年金事務所に届出 | 年金手帳・印鑑 |
| 住所・氏名が変わった時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 年金手帳・印鑑 |
| 年金手帳の再交付を受ける時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 印鑑・基礎年金番号の分かるもの |
第2号被保険者
|
どんな時
|
届出方法
|
用意するもの
|
|---|---|---|
| 60歳になる前に会社などを退職した時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 年金手帳・印鑑、離職証明など退職日の分かるもの |
| 勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者になった時 | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 年金手帳・印鑑、離職証明など退職日の分かるもの |
第3号被保険者
|
どんな時
|
届出方法
|
用意するもの
|
|---|---|---|
| 配偶者が退職した時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 年金手帳・印鑑、離職証明など退職日の分かるもの |
| 収入が増え被扶養者となった時 | 本人が役場国民年金係に届出 | 年金手帳・印鑑、扶養喪失日の分かるもの |
| 配偶者が転職した時、または配偶者の加入制度が変わった時 | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 年金手帳・印鑑または健康保険証 |
| 60歳になる前に就職して、厚生年金・共済組合などに加入した時 | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 年金手帳・印鑑または健康保険証 |
| 住所・氏名が変わった時 | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 年金手帳・印鑑 |
給付の種類について
年金にはどんな種類があり、どんな時に受け取ることができるのでしょうか。
| こんな時に受けることができます | 給付の条件 |
|---|---|
|
障害基礎年金
|
|
| 国民年金に加入している方や老齢年金を受ける資格のある方が、一定の障害の状態になった時 | 初診日の月の前々月までに加入しなければならない期間のうち、保険料を納めた期間と保険料を免除(学生納付特例期間を含む)された期間を合わせた期間が3分の2以上あること。ただし、平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。 |
|
老齢基礎年金
|
|
| 25年以上保険料を納めた方(免責期間も含む)が、65歳になった時。ただし、希望すれば60歳から減額して支給可能 | 国民年金保険料を納めた期間、厚生年金・共済組合加入期間などを合わせて、25年以上ある方が受けられます。 |
|
遺族基礎年金
|
|
| 国民年金加入途中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡した時に、その方が扶養されていた18歳未満(障害者は20歳)の子がいる配偶者または子に支給されます。 | 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あること。 |
|
寡婦年金
|
|
| 老齢年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した時 | 婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます |
|
死亡一時金
|
|
| 国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡した時 | 保険料納付済期間が3年以上あること。遺族が遺族基礎年金・寡婦年金を受けていないこと。 |