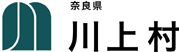公開日 2022年2月2日
弓祝式
約1100年の歴史を持つ地域の伝統行事。川上村指定無形文化財。 毎年、男性3名が弓の引き手に選ばれ、運川寺境内から40m離れた烏川神社境内の的に矢を放つ。
※2022年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者のみで開催いたしますので、一般の方の見学はご遠慮ください。
基本情報
| 開催日 | 毎年1月上旬 |
|---|---|
| 施設名 | 烏川神社(うがわじんじゃ、からすがわじんじゃ)、運川寺(うんせんじ) |
| 所在地 | 奈良県吉野郡川上村東川 |
1100年も昔、穏やかに暮らしていた村に突然悪魔(怪物)がはびこり領民を苦しめた。更に疫病が流行って多くの人々を苦しめた。
そこで、この山里に住む東弥惣(ひがし やそう)という弓の名人が、日頃信仰していた「白山大権現」の神力にすがるべく、延喜二(902)年六月、白山の向かいに三間四面の堂を築き、日夜、信心祈願を込めて祈った。延喜四(904)年、正月九日の朝方、弥惣は彼方に悪魔の化身を見、「天佑神助のお陰」と折からの大雪をものともせず、蓑笠をつけ、弓矢を持って悪魔を退治した。村人は弥惣の功をたたえて酒と雑煮でもてなした。
その時弥惣は「悪魔は山の主である。今後も村に祟りをもたらすかもしれないから、毎年正月九日に、桑弓、蓬矢で東西南北、天地の間を射て、悪魔降伏を行え」と悪魔降伏の神術を教えた。 それより、一月九日を悪魔払いの祝いの日と定め、弥惣が教えた古式によって、千破美(ちはみ)の蓑笠をこしらえ、千破美の踊りをとり入れて桑弓、蓬矢の射込み式を行い、最後に運川の僧侶が鬼の供養の読経をして引導を渡す。