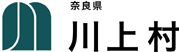公開日 2017年12月5日
2017年12月4日(月)くもり
後南朝の歴史を訪ねて、柏木地区を歩きました。
川上村では毎年2月5日に『朝拝式』が執り行われています。自天王遺品の甲冑や刀剣を前に悲運の皇子 自天王と忠義王を偲びます。1458年以来560年も続く、伝統ある行事です。
現在は金剛寺で行われる朝拝式ですが、寛永二年(1625年)までは御座磧(ござがわら)と呼ばれる、吉野川で執り行われていました。柏木の御座橋(ござばし)を渡り、川沿いの道を上流に進むと若年神社があり、若年神社からは御座磧に降りる石段が築かれています。御座磧の対岸に見える岩山は御座嵓(ござぐら)、舞楽を奏した場所は舞場と呼ばれています。
【若年神社】
若年神社・・・『更矢文書』によると自天王の即位式が行われた場所に建立された神社と伝わります。
【御座磧(ござがわら)】
【御座嵓(ござぐら)】